米沢の郷土料理
山国米沢。その独特の郷土料理は、まさに鷹山公の「かてもの」から受け継がれた知恵と工夫の賜物なのです。
米沢の郷土料理
※五十音表記
吾妻竹
いも煮
いも煮鍋を囲んで野外パーティーを開くことを、いも煮会と呼び米沢の秋の風物詩となっている。
里芋・コンニャク・長ネギ・キノコ・牛肉等を材料とした醤油味の鍋だが、味噌を少々加えることもある。
うこぎ
低木の落葉樹。鷹山公の教えの一つでとげがあることから、垣根にもなり若芽は食用にもなる。
ミジンに切って焼味噌と切り和えにしたり、御飯にまぜこんでうこぎ御飯・てんぷら等にし、根は五加皮という漢方薬にもなる。
おみ漬け
近江の商人が紅花を買い付けにきた際に伝えていったものと言われており、青菜・人参・大根などを浅漬けにしたもの。青菜とは、高菜科の野菜。
丘ひじき
置賜・村山地方特産の野菜。形が海草のヒジキに似ていることから、丘ひじきとよばれている。
カラカイ煮
カラカイとはエイを干したもので、煮込んで、煮汁はニコゴリとなる。正月料理。
くきたち
菜の花。おひたしにしても可。干して保存食。
窪田丸茄子
窪田地方で採れる小茄子。皮が薄く歯触りがよいのが特徴で、茄子漬けといえば塩で漬ける一夜漬けのこと。
鯉のかば焼
上杉伯爵邸オリジナル。
鯉には小骨がたくさんあるが、それをあえて抜くことをせず、包丁をいれ刻んでいき、それを、かば焼にしたもの。小骨の舌触りと肉のやわらかさ、特製のタレでじっくり焼き上げたかば焼は、鯉料理の逸品である。
鯉せんべい
鯉の洗いを唐揚げにしたもの。
ごんぼざみ
山菜の一種。菜は捨てて、茎を食す。
御飯(上杉籍田米)
米沢の塩井町というところに、農家の集まりで“米沢稔りの会”がある。消費者により安全で、より美味しい米をお届けしたいという主旨で結成され、有機農法、低農薬米を栽培している。その米を上杉籍田米と命名。
山菜・きのこ
みずな・しおで・こごみ・タラの芽・山ウド・あいこ等山菜物は通常おひたしにして食すが、てんぷらや胡麻和えにしても美味。
わらびやぜんまいは、干したり塩漬けにて保存する。きのこは塩蔵する。
塩引寿司
米沢では鮮魚が手に入らないことを逆手にとって、塩引きを使う。紅白に成ることから正月やめでたい席に出す。
つぶつぶ煮
冠婚葬祭など人の集まった時に出す料理。
いも子・人参・平コンニャク・牛肉などを醤油と酒で煮込んだもの。
伝統野菜
古志田のゆきな、遠山のカブ、南原のそば、小野川の豆もやし、ずさ山の大根、塩井のせりなどその地区の特産とされているものが数多くある。
また、現在生産されていないものもある。
農家の方の協力のもと復活させた遠山カブは、上杉伯爵邸でしか味わえない。
冷汁
米沢の代表的郷土料理のひとつ。冠婚葬祭や行事の欠かせないもので、その由来は、陣中料理とされる説がある。
ゆでた季節の野菜に、貝柱と干し椎茸でとっただし汁をかけて食す。材料は食用菊・雪菜・豆もやし・ナメコ・凍みコンニャク等使用するが、季節や各家庭により異なり決まりがない。
凍みコンニャクとは、高野豆腐のコンニャク版で、日本で一件の農家でしか作っておらず、置賜地方でのみ食用としている。
ヒョウ干し煮
和名スベリヒユと言う雑草。独特の酸味とぬめりが特徴で、初夏に採れる。おひたしにして辛子醤油で食べるのが一般的だが、鷹山公時代からの習いで、干して保存食にもする。
ヒョウの干し物は“ひょっとして良いことがあるように”“拍子が良いように”との意味あいを込め出す正月料理。
氷頭なます
塩引寿司に使った塩引の頭を取って置き、大根・人参の千切りと混ぜて甘酢に2,3日漬け込んだもの。大根の白、人参の赤とで紅白となり、正月に出す。
紅花御飯
紅花とは、最上紅花のことをいい、最近では観賞用の紅花も出てきたが、それとは区別されている。紅花の若芽は食用となり、花弁は染料となります。御飯にまぜこんだり、紅花酒にしたりと食用や漢方薬にも利用する。
棒ダラ煮
鮮魚が手に入らない米沢では、海の魚の干し物でも大変貴重な保存食となる。
棒ダラ煮は、お盆の時に出す料理といわれ、鱈の干物を水で戻し、じっくり煮込んで出す。
ゆきな
ゆきなには、かぶをとうだちさせたものと、越後菜(アブラナ科)をとうだちさせたものの2種類あり、現在は越後菜の方が一般的。
上杉氏が郷里から持ち込んだとか、鷹山が越冬用に栽培させたとかの説があるが、記録には残っていない。
一つの野菜の食用期を犠牲にした贅沢な野菜。ふすべて辛みを出す雪菜のふすべ漬け、お浸しにして食する。冷汁に入れる場合もある。
米沢鯉
米沢鯉は、池で放育していたものを捕獲し、吾妻の清流から引いてきた水の中に一旦放し泥抜きをする。その為、味が良くドロ臭さの全くない物となる。
甘煮は、脂ののった真冬の鯉を輪切りにし、各家庭で甘露煮にした正月料理だが、病人や出産後の婦人などにもだす。
リンゴ漬け
遠山のリンゴ(光玉・国光)を塩漬けにしたもの。主に落ちリンゴを使用する。
お問い合わせ
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
受付時間 11:00~21:00
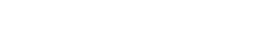






吾妻の麓で、春から初夏にかけて、細竹の子が採れる。シャキシャキとした歯触りで、煮物・竹の子御飯・てんぷら・サバの缶詰とともにみそ汁に入れたり、味噌をつけて焼く田楽などにして食べる。